
-
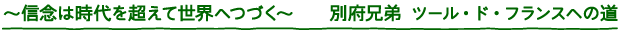
世界を熱狂させたツール・ド・フランス2010最終ステージ。
日本人初となる別府史之のツール・ド・フランス敢闘賞受賞へとつながるパッション。
常に最も身近で、冷静に見つめつづけて来た別府始の視点を通し、
世界的なアスリートへつながる道へインサイトしてみたいチャンスとのめぐりあい
 チャンスと同様に、きっかけとは偶然、眼の前に現れるものなのかもしれない。
チャンスと同様に、きっかけとは偶然、眼の前に現れるものなのかもしれない。
別府始と匠、そして史之。後年、日本のスポーツ自転車文化をそれぞれの力で支えることになる三人の兄弟と自転車との関わりも偶然もたらされたものだった。
1990年のある日、父親の友人が17キロ離れた隣町から自転車で遊びに来た。現在の彼らにすればウォーミングアップにも物足りない17キロ、しかし、少年たちに衝撃を与えるのには充分な長距離でもあった。衝撃、憧憬、そして興味へ。
知識は興味を持つ人へと集まるものなのだろう。そして、時代も彼らの背中を押した。この頃、世界最高峰の自転車ロードレース『ツール・ド・フランス』がNHKで放映され、また、世界選手権が宇都宮で開催されたこともあり、彼らの興味という視界に世界が映っていたことを僕たち自転車好きは感謝するべきだろう。
実際、彼らの胸にはじめて刻まれたあこがれの選手こそが、スポーツ大国アメリカ初の世界チャンピオン『グレッグ・レモン』であり、欧州から世界へと拡がる転換期を象徴する人物であったことも、BEPPUというエキゾチックな響きで世界に衝撃を与えている今、不思議なめぐり合わせのように感じてしまう。
一年後。はじめて出場した自転車レース大会で始と匠はそれぞれのカテゴリーで入賞し、はじめて自分の力で手にした商品を前に眼を輝かせていた。当時、小学2年生だった史之は身体の大きな上級生たちの背中をみながら15位でレースを終えたという。始は当時を振り返り『フミ(史之)はいきなり、そして相当悔しい想いをしたから今がある』と語った。
愉しさをやりがいに、悔しさをバネに、彼ら兄弟の道は今へと続いている。

世界への道
 黒髪の日本人がシャンゼリゼを駆け抜ける。人気漫画の頁に広がったひとつの風景、それは始にとって鮮烈なイメージとして心に刻まれ、いつしか明確な目標となった。彼の素晴らしさは、この目標を自己に投影するのみならずプロデューサー的な視点により兄弟全体で共有するものへと昇華させたことであろう。
黒髪の日本人がシャンゼリゼを駆け抜ける。人気漫画の頁に広がったひとつの風景、それは始にとって鮮烈なイメージとして心に刻まれ、いつしか明確な目標となった。彼の素晴らしさは、この目標を自己に投影するのみならずプロデューサー的な視点により兄弟全体で共有するものへと昇華させたことであろう。
中学一年生の春、史之は遥かに大きな三年生も居並ぶ大会で優勝を遂げた。この時にはすでに、漠然としたイメージが明確な目標に変わっていたことを始は振り返る。
「フミはツール・ド・フランスにチャレンジしなくちゃいけないと明確に意識した」
その後、別府三兄弟をめぐる叙事詩は世界との関わり抜きには語れないものとなる。「フミが中学生3年生となったころ、タクミが高校を卒業してヨーロッパへ渡るタイミングだった。」始が語るように、この時代、彼らの先輩となる実業団の選手たちが続々とヨーロッパへ挑戦し、そして帰ってきた。挫折というほろ苦い経験を持って。 匠がヨーロッパへ先輩の背を追うように向かった時、始は大学生であった。
第一線で弟たちが活躍し、挑戦に眼を輝かせる中、大学生として過ごす始の胸をさまざまな葛藤が満たす。なにをしているのか?なにをすべきなのか?
そんな時、雑誌ファンライドの編集部からアルバイトの誘いを受けた。またも偶然とも思えるきっかけ、しかし、進むべき道を歩んできた彼にとって、この機会は在るべき道への誘いだったように僕は感じる。そう偶然なんかじゃない。
始はこの日以来『別府始というメディア』を目指すことになる。
事実、その日以来、彼はメディアの第一線に居つづけ、そして、弟たちのマネジメント担うエージェントとしての顔も持ち、さらにプロスポーツとしての自転車の地位向上を目指すスポークスマンとしての顔も持っている。 2009年、ツール・ド・フランス最終ステージ。シャンゼリゼを駆け抜ける黒髪の日本人がパリの街を熱狂の渦へと巻き込んだ。別府史之はこの日、果敢にアタックを行い、日本人初のステージ敢闘賞を手にした。 彼ら兄弟が自転車レースに飛び込んだ時代には誰も想像できなかった事。日本人がツール・ド・フランスを走る。日本人がシャンゼリゼで独走する。日本人がツール・ド・フランスを完走する。日本人が表彰台に立つ。そして、数多くの日本人が、自転車レースファンが、フランスからライブのように送られる始のTWITTERに熱狂する。
選手とメディアという役割の違い。選手とマネージャーとしての役割の違い。始が葛藤の中で見出した自分の歩むべき道「メディアとしての人」が文化を育て始めている。
僕たち自転車好きは、別府三兄弟をこれからも注目し声援を送り続けるだろう。これからも別府始というメディアがリードし続けるのだからtext by Kaoru Eshii